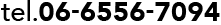エフェクチュエーション?
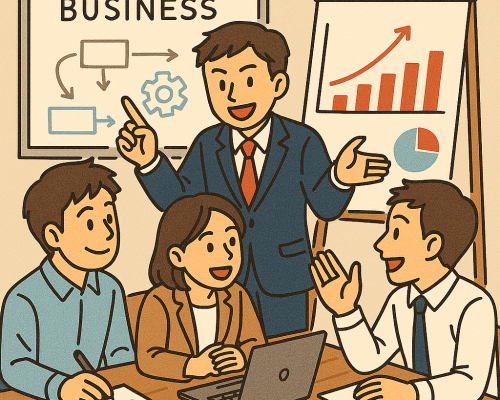
現在社内では将来に向けての新しい収益事業の検討を行い、実現に向けて準備が整いつつあるものがあります。 会社の柱となる新聞即売事業も(今さらですが)新聞を取り巻く環境の変化に抗うことができず今のままでは将来安心できない状態です。堺筋本町にある『大阪産業創造館』では大阪府内の企業を対象として様々な新規事業についての相談を受付けています。その産創館のセミナーの中で税理士の神佐真由美先生という方の講演を聴講したことがきっかけで神佐先生の週一回のメールマガジンを愛読しています。
今回はその中のお話です。
通常の会社の経営スタイルは「目標を立てて、そこから逆算して最適な道を選ぶ」という理論が一般的です。
しかし今の不確実な時代、「計画を立てたのに、お客さんの反応が予想と違った」、「そもそも前提としていた
ことが崩れた・・・」と計画通りに物事が進むことの方がむしろ珍しいといってもいいかもしれません
こんな時代にどうやって意思決定すればよいのでしょうか? アメリカのバージニア大学、ビジネススクールのサラス教授は次のような理論を提唱しました。それは「状況が不確実で予想が困難な中でも、手持ちの資源と関係性を生かしながら柔軟に進んでいく」という実践的な意思決定のロジック。これをエフェクチュエーション=“実行主義”と言うそうです。(初めて聞きました) これは今あるものを棚卸する、できることから始める、
その中で出会った人や反応に応じて柔軟に方向を変えていくという「まず動いてみる」スタイルの戦略です。
この戦略は5つの原則にまとめられています。
① 手中の鳥の原則→すでに持っている「知識」「ネットワーク」「スキル」から出発する
② 許容可能な損失の原則→大きな利益よりも、「失ってもいい範囲」で挑戦する
③ クレイジーキルトの原則→一緒に何かを作れる仲間を早い段階で巻き込む(仕入先や地元企業とコラボ)
④ レモネードの原則→予期せぬ出来事や失敗をチャンスに変える
⑤ 飛行機の操縦士の原則→未来は自分の行動次第、「予測」より「コントロール」を重視する
いかがでしょうか?イメージが膨らみませんか?
この考え方を社内に落とし込むとすると①完璧よりもまずやってみる②オープンな対話の場を作る
③リソースを共有する④失敗を責めない、小さな成功を称える。こんな風土ができると一人一人がまずやってみようという姿勢を持てると思います。予測困難な時代でも柔軟に対応できる組織を育てていきたく思います。
内田秀一